
愛猫との別れは、心にぽっかりと穴があいたような、言葉では言い表せない寂しさを伴うものです。急な出来事に戸惑い、どう見送ってあげればよいのか分からず、不安になる方も少なくありません。長く一緒に過ごしてきたからこそ、最後の時間も大切に過ごしたいと願う気持ちは自然なことです。
この記事では、ペット葬儀の中でも猫の「火葬」に注目し、「合同火葬」と「個別火葬」の2つの方法について、その違いや流れ、それぞれの特徴を踏まえた選択のポイントを解説します。
後悔のないお別れのかたちを考えるきっかけとして、お役立ていただければ幸いです。
猫の火葬は2つに分けられる|合同・個別
愛猫を見送る方法には、「合同火葬」と「個別火葬」の2つの選択肢があり、それぞれに特徴があります。火葬の費用や立ち会いの可否、遺骨の取り扱いなどが異なるため、愛猫とのお別れになにを望むかによって、選ぶべき火葬方法も変わります。

まずは、それぞれの火葬方法の特徴を見ていきましょう。
猫の合同火葬|複数の猫を同時に火葬
合同火葬とは、同時期に亡くなった複数のペットと一緒に火葬をおこなうことです。
主に自治体や保健所などの公的機関によって提供されており、費用が比較的抑えられることを理由に利用する方が多いサービスです。金額は自治体によって異なりますが、数千円程度から利用できるケースが多く、経済的な負担をできるだけ抑えたい方にとって、ひとつの選択肢となっています。
また、「気持ちの整理がつかないまま見送らなければならない」「静かに、そっとお別れしたい」といった想いを抱える中で、この方法を選ばれる方も少なくありません。立ち会いやセレモニーを行わず、最小限のかたちで送り出したいと考える方にも合った方法です。
ただし、複数のペットを同時に火葬するため、火葬後の遺骨は返骨されません。そのため、遺骨を持って帰ってきてご自宅で供養したいご家族などには適さない火葬方法といえるでしょう。
なお、利用の可否や申し込み方法は自治体によって異なりますので、事前にお住まいの自治体にご確認いただくことをおすすめします。
猫の個別火葬とは|一匹ごとに火葬
個別火葬は、他のペットと一緒にせず、愛猫だけのために火葬を行う方法です。さらにペット火葬業者によっては、ご家族の希望に応じた読経や焼香などのセレモニーを取り入れたお別れもできます。
火葬への立ち会いが可能なこともあり、最後の瞬間をそばで見届けたいというご家族に選ばれることが多い火葬方法です。火葬後には、遺骨を骨壺などに収骨する「お骨上げ」ができる場合もあり、ご遺骨はそのまま返却されます。
その後は、ご自宅での手元供養のほか、ペット霊園や納骨堂への納骨、自然葬(散骨)など、希望に応じた供養のかたちを選ぶことができます。
さらに、専用の火葬車で自宅まで訪問してくれる「訪問火葬」に対応している業者もあり、外出が難しいご家庭にも配慮されたサービスもあります。
自分たちらしいかたちで過ごしたい方にとって、個別火葬はその想いに寄り添える選択肢のひとつです。
火葬方法の選び方|メリット・デメリットを比較

「合同火葬」と「個別火葬」には、それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶかは費用面だけでなく、ご家族の想いや供養の考え方によって異なります。
参考までに主な違いを以下の表にまとめましたので、火葬方法を選択する際にお役立てください。
【合同火葬と個別火葬の違い】
| 項目 | 合同火葬(主に自治体) | 個別火葬(主に民間業者) |
|---|---|---|
| 火葬の方法 | 複数のペットをまとめて火葬 | 個別に火葬 |
| 実施機関 | 自治体・保健所などの公的機関 | 民間のペット葬儀業者 |
| 費用の目安 | 比較的安価(数千円〜) | 業者によるが2万円〜数万円程度 |
| 遺骨の返却 | 基本的に不可 | 可能 |
| 火葬への立ち会い | 不可 | 可能 |
| セレモニー | 不可 | 読経・焼香・花や手紙の同封など柔軟に対応可能 |
| 訪問火葬 | 非対応 | 業者によっては対応 |
合同火葬は、費用の負担を抑えて見送りたい方に選ばれることの多い方法です。一方で、愛猫との最後のひとときを静かに過ごしたいという想いから、個別火葬を選ぶ方もいらっしゃいます。
猫が亡くなった後の適切なケア方法

愛猫が息を引き取った直後は、心の整理が追いつかず、何をどうすればいいのか分からないという方も少なくありません。大切なのは、慌てずに「最後まで寄り添う」気持ちを持つことです。
お別れまでの時間を穏やかに過ごすために、ご家族がしておくべきケアについて確認しておきましょう。
猫の死亡直後にするべきこと
愛猫が息を引き取った直後、まずはご家族で静かにその時を受け止めることが大切です。そして、できるだけ早い段階で体をやさしく整えてあげましょう。
死後硬直は数時間以内に始まるため、それまでに以下のようなケアを行っておくと安心です。
- 手足を自然な姿勢に整える(丸くなった姿勢や仰向けなど)
- 毛並みを軽く整え、顔まわりを拭いてあげる
- お気に入りのタオルや毛布でくるんであげる
特別な準備が整っていなくても、ご家族でそっと語りかけたり、なでてあげたりする時間は、心の区切りにもつながります。
猫の適切な安置や保冷方法

火葬や葬儀まで少し時間が空く場合、体を清潔に保ちつつ、適切に安置・保冷することが大切です。まずは、保冷剤やドライアイスをタオルで包み、お腹のあたりを中心にあててあげましょう。お腹は特に体温が下がりにくいため、重点的に冷やすことで体の状態を保ちやすくなります。
また、体液漏れなどによる汚れを防ぐため、体の下にペットシートや防水シートを敷くことをおすすめします。安置場所は直射日光を避け、できるだけ涼しい部屋を選びましょう。
体液のにじみやにおいが気になる場合もありますので、タオルやシートをこまめに取り替えながら、衛生面にも配慮することが重要です。
お別れの準備を進めるなかで、「何もしてあげられなかった」と感じる方もいますが、そばにいて見守ることそのものが、何よりの供養になります。
なおペット火葬・葬儀社の中には、ご安置・保冷から任せられるプランを用意しているケースも少なくありません。ご安置中の対応に不安を感じる場合は、こうしたプランを利用するのも選択肢の1つです。
猫の葬儀・火葬の基本的な流れ

愛猫が旅立ったあと、何をどう進めていけばいいのか分からず、不安になる方も多いのではないでしょうか。そのような場合でも、火葬の流れや準備について知っておくことで、気持ちを整理しながら、落ち着いて見送りの準備を進めることができます。
ここでは、葬儀社を選ぶところから火葬、そしてその後の供養までの一般的な流れをご紹介します。
(1)葬儀社を選ぶ
まずは、信頼できるペット葬儀社を選ぶことから始まります。対応エリア、火葬方法(合同火葬・個別火葬)、料金、訪問可否、セレモニーの有無など、事前に確認しておくポイントは多岐にわたります。口コミや紹介、実際に問い合わせをしてみた印象なども参考にしながら、納得のいく業者を選びましょう。
(2)葬儀社へ連絡を行う
葬儀社が決まったら、連絡を入れて火葬やお迎えの日時を相談します。中には24時間対応している業者もあり、急な連絡でも柔軟に対応してくれることが多いです。この段階で、希望する火葬方法やセレモニーの内容、料金などを確認しておくと安心です。
(3)猫の葬儀セレモニー|読経・焼香など
個別火葬を選んだ場合、多くの葬儀社ではお別れのセレモニーを行うことができます。読経や焼香、お花や愛猫の好きだったおやつをお供えするなど、ご家族それぞれの想いを込めて送り出す時間を過ごせます。ご家族の気持ちに寄り添ったかたちで、愛猫に「ありがとう」と伝える時間になります。
(4)猫の火葬とお骨上げ
ペットの火葬が行われている間は基本的に、別の部屋で待つことになります。ご自宅への訪問火葬サービスをご利用の場合は、ご自宅で待つことが一般的です。
お骨上げでは、ご遺族の方々が専用の長箸を用いて、ペットの遺骨を丁寧に拾い上げ、骨壺へと納めていきます。この流れは人間の葬儀と同様です。訪問型の火葬サービスにおいても、お骨上げができるプランが多数ご用意されており、ご自宅近辺で最期の瞬間まで寄り添うことが可能となっています。
なお、火葬には以下のように、猫の体格に応じた時間がかかります。
🔸 猫の火葬時間の目安(個別火葬の場合)
※葬儀社によって異なるため、あくまで目安です。
| 体格の目安 | 火葬時間の目安 | お骨上げまで含めた所要時間 |
|---|---|---|
| 小柄な猫(~3kg程度) | 約30〜50分 | 約1〜1.5時間 |
| 中型の猫(3〜6kg) | 約45〜60分 | 約1.5〜2時間 |
| 大きめの猫(6kg以上) | 約60〜90分 | 約2〜2.5時間 |
(5)猫の遺骨の取り扱いとさまざまな供養方法
火葬後に返骨された遺骨は、ご家族の想いに応じてさまざまなかたちで供養することができます。具体的には以下のような供養が一般的です。
- 手元供養:骨壷を自宅に置き、いつでもそばに感じられる方法
- 納骨堂への納骨:ペット専用の霊園や納骨堂に安置する方法
- 合祀墓(ごうしぼ):他のペットたちと一緒に埋葬される供養
- 散骨:自然の中に還す方法(海や山など、許可が必要な場合も)
どの方法にも「正解」はありません。ご家族それぞれの気持ちや環境に合ったかたちで、愛猫を想い続けていくことが大切です。
猫が亡くなった後に行う公的手続き
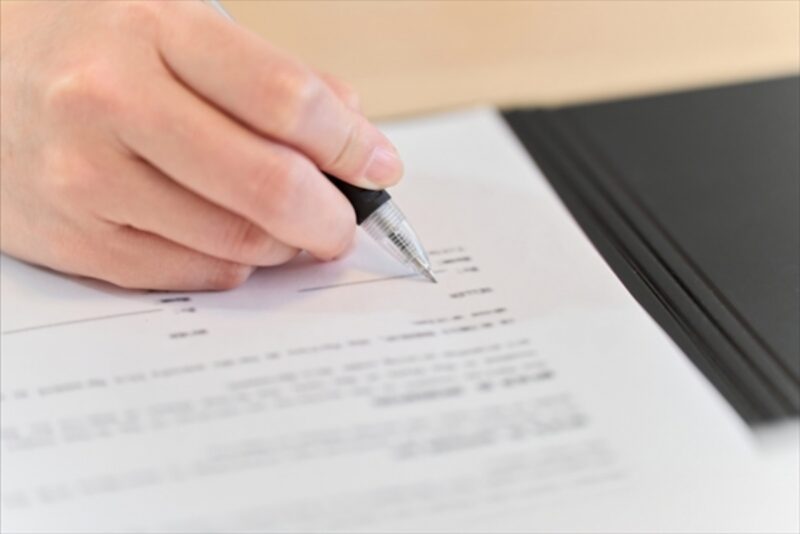
愛猫とのお別れは深い悲しみの中で迎えることが多く、心の整理も追いつかないまま時間が過ぎていきますが、必要な手続きを知っておくことで、少しずつ日常に向かって歩み出すことができます。
ここでは、愛猫が亡くなった後に必要となる公的な手続きについてご紹介します。
マイクロチップの手続き
愛猫にマイクロチップを装着していた場合は、登録情報の変更・抹消手続きが必要です。マイクロチップの情報は「環境省データベース」や「民間登録団体」によって管理されていますので、登録されている団体を確認し、所定の方法で抹消申請を行いましょう。
手続きには、以下のような書類や情報が求められることがあります。
- 飼い主の氏名・連絡先
- 猫のマイクロチップ番号
- 死亡日を記載した申請書または届出書
登録団体によって手続きの方法や必要書類が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
猫の場合は死亡届は不要
犬の場合は自治体への登録が義務付けられているため、死亡時に市区町村へ「犬の死亡届」を提出する必要がありますが、猫に関しては法的な登録義務がないため、死亡届を提出する必要はありません。
ただし、地域によっては飼い猫に関する独自の制度を設けている場合もあるため、不安な方は念のためお住まいの自治体に確認してみてもよいかもしれません。
民間ペット火葬業者の選び方

愛猫を安心して送り出すためには、火葬をお願いする業者選びがとても大切です。事前にしっかりと情報を集めて、信頼できる業者を選ぶことが第一歩となります。
ここでは、火葬業者を選ぶ際に意識したいポイントや、比較・相談の際の注意点についてご紹介します。
信頼できる葬儀社を選ぶポイント
民間のペット葬儀業者は数多くありますが、その中から自分たちの想いに寄り添ってくれる業者を選ぶには、いくつかの基準を確認しておくことが大切です。
以下のポイントを参考にしながら、安心して任せられるかどうかを判断してみましょう。
- 実績や経験の豊富さ
長く運営されているか、過去の利用者の声が確認できるかを確認しておくと安心です。 - 料金体系のわかりやすさ
公式サイトやパンフレットなどに、火葬プランごとの料金が明記されているかを確認しましょう。曖昧な表現が多い場合は注意が必要です。 - 口コミや評判
実際に利用した方の声はとても参考になります。Googleマップや口コミサイトなどで、スタッフの対応やセレモニーの進行などの評価を確認してみてください。 - 問い合わせ時の対応
電話やメールで問い合わせたときの印象も大事な判断材料です。質問に丁寧に答えてくれるか、言葉づかいや態度に不安がないかをチェックしておきましょう。
事前の相談と見積もり比較の注意点

初めてペットの火葬をお願いする方にとっては、何が必要でどれくらい費用がかかるのか分からないことも多いはずです。そのため、事前相談や見積もり取得はとても重要なステップです。
比較検討の際に確認しておきたいポイントは以下の通りです。
- 複数の業者から見積もりをとる
1社だけで決めず、2〜3社から見積もりを取り、内容と金額を比較してみると安心です。 - 追加料金の有無を確認
基本料金のほかに、オプションや出張費がかかるケースもあります。見積もりにはどこまでが含まれているのか、当日の追加費用が発生する可能性はあるかなども確認しておきましょう。 - セレモニーの有無と内容
お別れの時間をきちんと設けてくれるかどうかや、その内容(読経・焼香など)を確認することで、自分たちの希望に合ったお見送りができるかを判断できます。
少しでも不明点や不安がある場合は、遠慮せずに質問をしておきましょう。大切な愛猫を託すからこそ、納得できる形で送り出せる業者選びがとても大切です。
火葬を依頼する前の確認チェックリスト

ペット火葬・葬儀社へ依頼をする前に、あらかじめ確認しておくべきポイントを整理しておくと、当日の流れもスムーズになります。大切な家族を安心して送り出すために、以下のチェックリストを参考に、事前の準備を整えておきましょう。
■火葬を依頼する前の確認チェックリスト
猫の葬儀・火葬についてよくある質問

葬儀の服装や持ち物にルールはある?
猫の葬儀には、喪服などの正式な服装を求められることは少なく、特別な決まりがあるわけでもありません。黒やグレーなど落ち着いた色味の服装であれば、問題ないとされています。華美すぎない、控えめな装いを心がけると安心です。
また、持ち物にも特別なルールはありませんが、お花や愛猫の写真、数珠、思い出の品などを持参される方もいらっしゃいます。形式にとらわれず、静かに愛猫を想う気持ちを大切にしてください。
猫と一緒に火葬できるものとできないものは?
猫と一緒に火葬できるものには、いくつか制限があります。お手紙やお花、少量のおやつ、布製のおもちゃなど、燃えやすい自然素材のものは一緒に火葬できることが多いです。
一方で、金属・ガラス・プラスチック類、たくさんの食べ物や大きなぬいぐるみなどは、火葬炉を傷める原因になるため避けましょう。思い出の品を入れたいときは、事前に火葬業者に確認することをおすすめします。
猫の葬儀に参列するときのマナーはある?
猫の葬儀に参列する際は、特別なマナーの決まりはありません。ただ、愛猫を亡くされたご家族の気持ちに寄り添い、静かに見送る心構えが大切です。服装は落ち着いたものを選び、大きな声や不必要な会話は控えましょう。お花やメッセージを添えると、飼い主さんの心にそっと寄り添うことができます。大事なのは、形式よりも気持ちです。
人間の葬儀のように香典や供花がある?
猫の葬儀では、人間の葬儀のように香典や供花を用意する決まりごとは特にありません。かしこまった準備は必要なく、飼い主さんの気持ちにそっと寄り添うことが何より大切です。それでも何か想いを伝えたいときには、白いお花や小さなメッセージを添えるなど、控えめなかたちで気持ちを届けることもあります。
まとめ
猫の火葬には、合同火葬と個別火葬という2つの方法があります。どちらを選ぶかは、ご家族の思いや状況によって変わってきます。「どう見送ってあげたいか」という気持ちに向き合いながら、自分たちらしいかたちを選ぶことが大切です。
費用をおさえたいときや、静かに送り出したいときには合同火葬という選択もありますし、お骨を手元に残したい、最後までそばにいたいという想いがあれば個別火葬を選ぶこともできます。
また、服装や供花、香典などの決まりごとはありません。形式にとらわれず、想いを自分なりに形にすることが、心に残るお別れにつながるはずです。
どんな選択であっても、大切なのは気持ちです。この記事が納得のいく見送り方を考える一助になれば幸いです。
《訪問火葬専門 ペットの小さな家》では、ペット葬儀や火葬に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。友だち追加するだけで、《ペットの小さな家》のディレクターに、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。

